

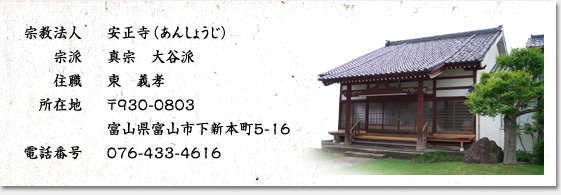
安正寺について
むかしの富山を読む・富山県立図書館
二十四輩順拝図
舘定山 極性寺 東派院家 古国府より五里半富山の城下にあり
本堂本尊阿弥陀如来 行基菩薩の作 塔中三区抑当寺開闘は往昔人皇六十代延喜帝の朝に牢臣藤原基経といふあり基経の三男徳麻呂 延基第二壬戌年行年十七歳にして世俗の交を遁れ高野金剛峯寺に登り弘法の教を学び三密喩伽の行法を得て 徳長院と号す。延基十九年已卯年当国新川郡舘の里に住せり。延長元年に同帝より舘定山極成寺宗帝院と勅額を賜り、伽藍を建立す是より七世の寺務を恵明院といふ。時に建保元年の頃高祖聖人越後越中所々住反して化導在ませしが一日彼 舘の伽藍を見給ひ 二王門の前なる立石に御腰をかけられ暫く休息し給ふ<一説には聖人越後へ御下向の時 此里を過給ふといふ>
塔中の安正院『誓空』といふ僧門内よりこれをみれば門の左右なる二王の像一向腰をかがめて聖人を拝ませるがごとし安正院 奇なる事に思ひ其まま走り入て寺務にかくとつげれば恵明院立出て是をみるにその詞に違ふ事なしこれ実に凡僧ならざる事を知りて即聖人に面謁す聖人其宗旨を間給ふ恵明院答ふるに詠歌を以てす
我法は賤山婦の九十九髪結ふもいわれず解もとかれず
聖人此歌の意を得て扨は 真言天台難解難行の宗旨 他と知り給ふ恵明院聖人 答へて
我法は朝夕撫し児の髪ゆふるいはるる 解もとかるる
となん返 歌し給ふ爰におひて恵明院いよいよ凡僧ならずと知り事に請し奉り終夜 問答往復し実に他力易行の教行は末法五濁の要法なる事を聴聞せられしより立所に本宗を改め宗門に版し御弟子と成りぬ 聖人即 法名を教順と授け給ふ扨聖人 此寺を出給ふ時、教順坊も御供申 宮崎といふ所に宿し給へり爰に極性寺累代の門徒三人此事を聞 御跡を慕ひ宮崎に至り御教化を聴聞して御弟子と成れり聖人 此三人にも法名をたまわりける稗畑村の定相《末孫今の名は七郎左衛門といふ〉室田村の寂念《末孫の名は五郎右衛門といふ》念名《末孫の名は九郎右衛門といふ》是なり当時は法名を家名として子孫相続し 今に極成寺の門徒たり教順房は聖人を供奉し越後国府に至り
翌年五月本坊に帰 寺号を極性寺と改む 其後乱世の刷舘の里の諸堂兵乱の災に掛り所所に移住すといえども其寺系を失はずして第十六世の住持良恵の時 寛永元年に当所富山愛宕町へ移住して祖師の法灯を伝ふるものなり

